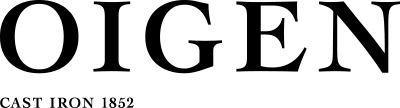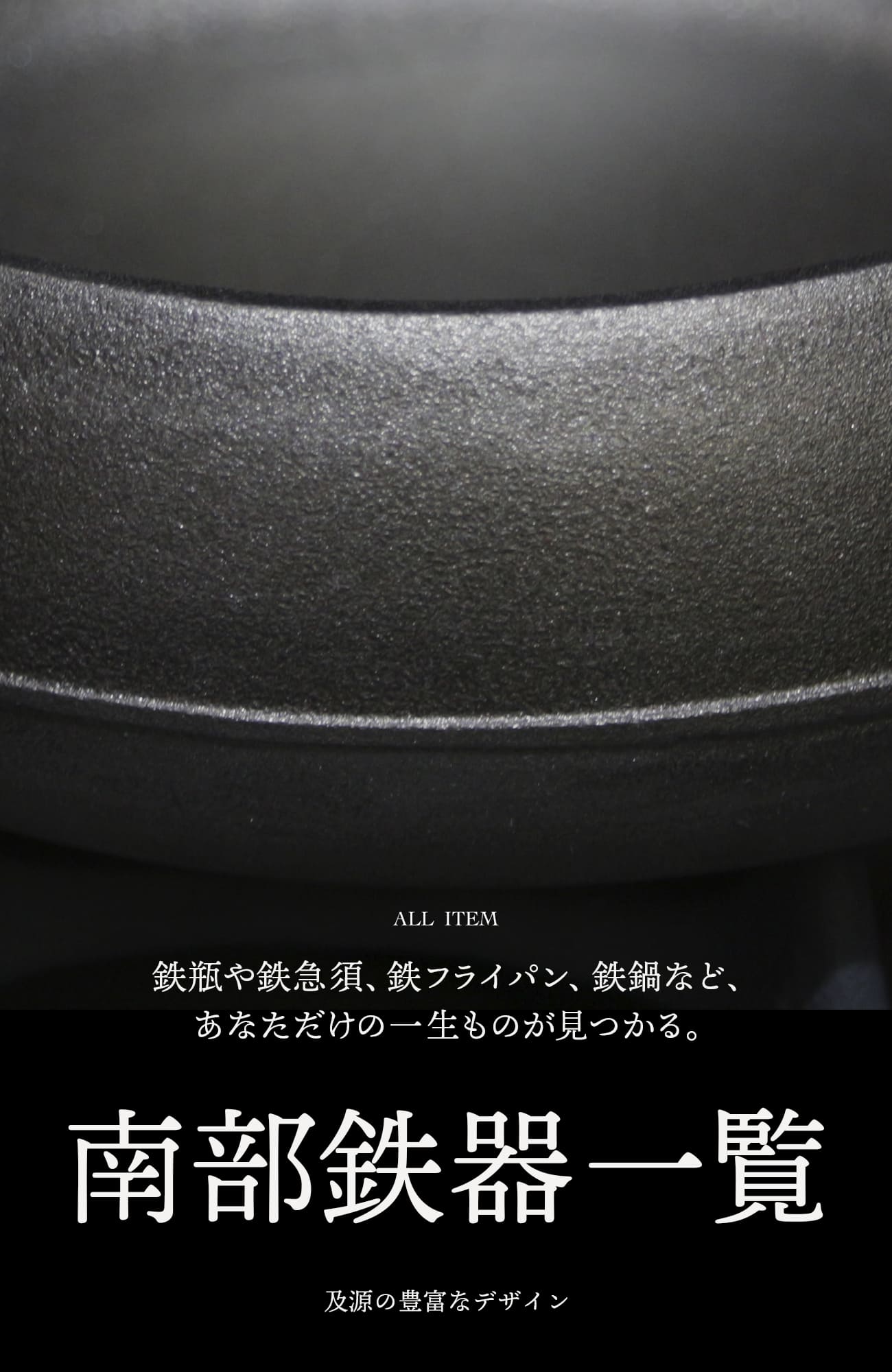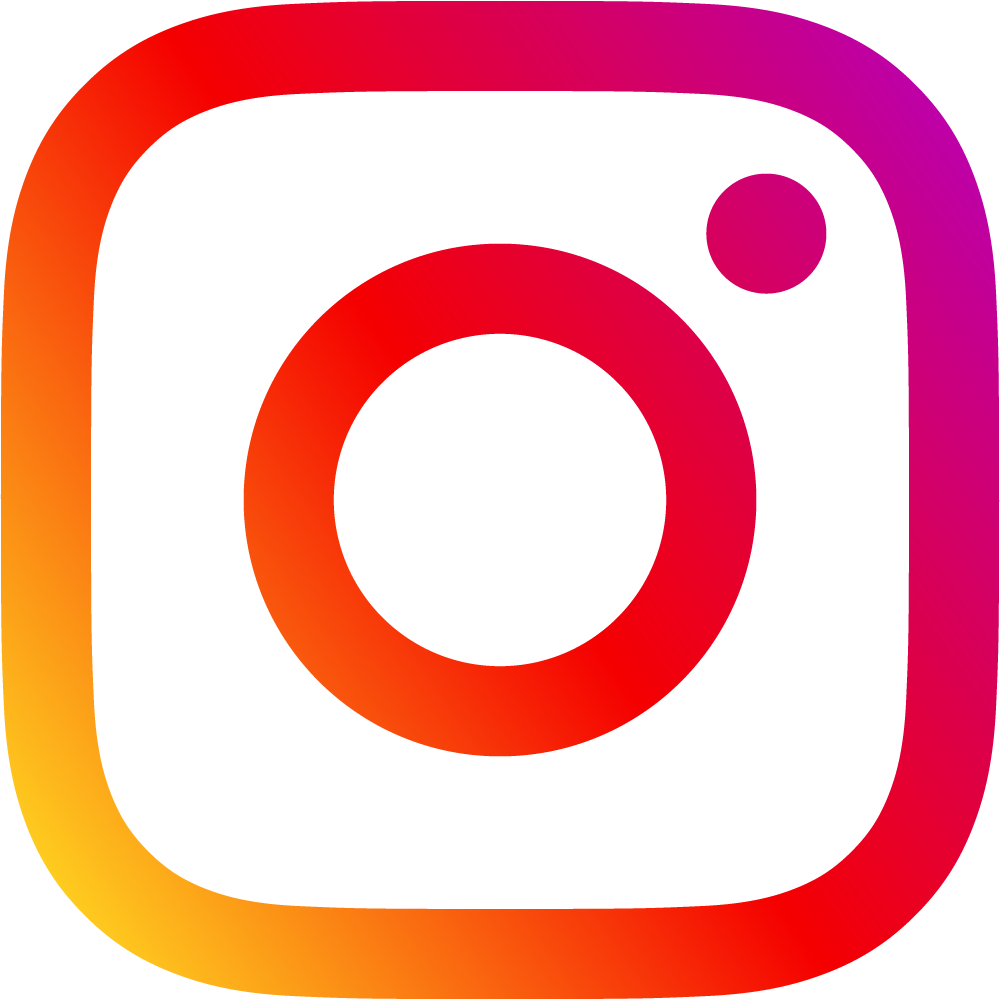南部鉄器の老舗「及源鋳造」 約90年前の創業家・及川家 上の写真で左にいる鉄瓶の蓋を頭に載せて喜んでいる少年が、約90年前の及源鋳造の現会長・及川源悦郎、現代表・及川久仁子の父です。その会長が、こんなに小さかった頃の暮らしを聞いてみました。 「食事は鉄羽釜で炊いたご飯と、鉄鍋で似たお煮しめ、鉄鍋で作ったお汁。時には煮魚もあったな…。鉄羽釜のご飯は、鉄竈で炊いていた。 ―うん? 「そう。当時...

水沢で生まれた南部鉄急須 保温性が高く、優れたデザイン性を持つ南部鉄器の鉄急須。鉄器の中でも特に気軽に使用できることから、日本のみならず海外でも人気のある商品です。 急須は茶器。そのため、茶道具や贈答品として発展してきた盛岡の鋳物から発祥したイメージを持ちますが、「実は鉄急須は水沢にもある」。 そう話すのは、OIGEN会長の及川源悦郎さん。なぜ鍋や釜など民衆品として発展してきた水沢に...

日本での煮沸調理法は縄文時代から続く伝統レシピである。 縄文時代の煮沸具といえば、もちろん“縄文土器”であるが、弥生時代以降に鋳造技術を手に入れてからは、次第にその主役は鉄製の鍋釜へと移り変わっていった。もちろん、現代の煮沸具における鍋釜の存在はもはや不動の地位である。 遺跡から出土する煮沸具には、鉄製・土製・石製などバリエーションが豊富である。水沢玉貫(たまぬき)遺跡から出土した鉄...

かつて、この川は砂鉄の採掘で賑わった。 砂が舞い上がり、水が濁ったため「にごり川」とも呼ばれていたこの川の名は「砂鉄川 。いわてのものづくりをずっと見つめ、支えてきた。時は流れ、今では澄んだ水が静かに流れている。 写真|文・橋本太郎

岩手を代表する、はたまた日本を代表する伝統工芸品の一つである「南部鉄器」。現在では、美味しい料理を作る道具として、または鉄瓶等の文化的価値の高さで、世界中で評価を得ています。 岩手では、台所に南部鉄器のすき焼鍋や鉄瓶が、茶の間には鉄の急須がある。そんな家庭が珍しくはないくらい、「南部鉄器」が、暮らしにとってごく身近な生活の道具なのです。しかし、「南部鉄器」に馴染みの深い岩手県民でさえ、「いつ...

「南部鉄器」の物語(後篇)-南部鉄器のターニングポイント
前章の南部鉄器の物語(前篇)では、南部鉄器の二大産地それぞれの起源や略史、特徴を紹介しました。今回は「南部鉄器」が辿ってきたその道筋をさらに深く探るべく、南部鉄器のターニングポイントに迫っていきたいと思います。 目次 2つの南部鉄器「水沢の鋳物」と「盛岡の鋳物」 鉄薬鑵てつやかん(南部鉄瓶)の誕生|江戸期 明治の転換期|明治期 盛岡大火|明治期 鉄瓶黄金時代|大正期 太平洋戦争|昭和期...