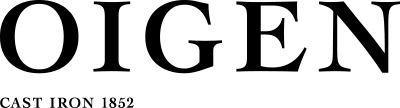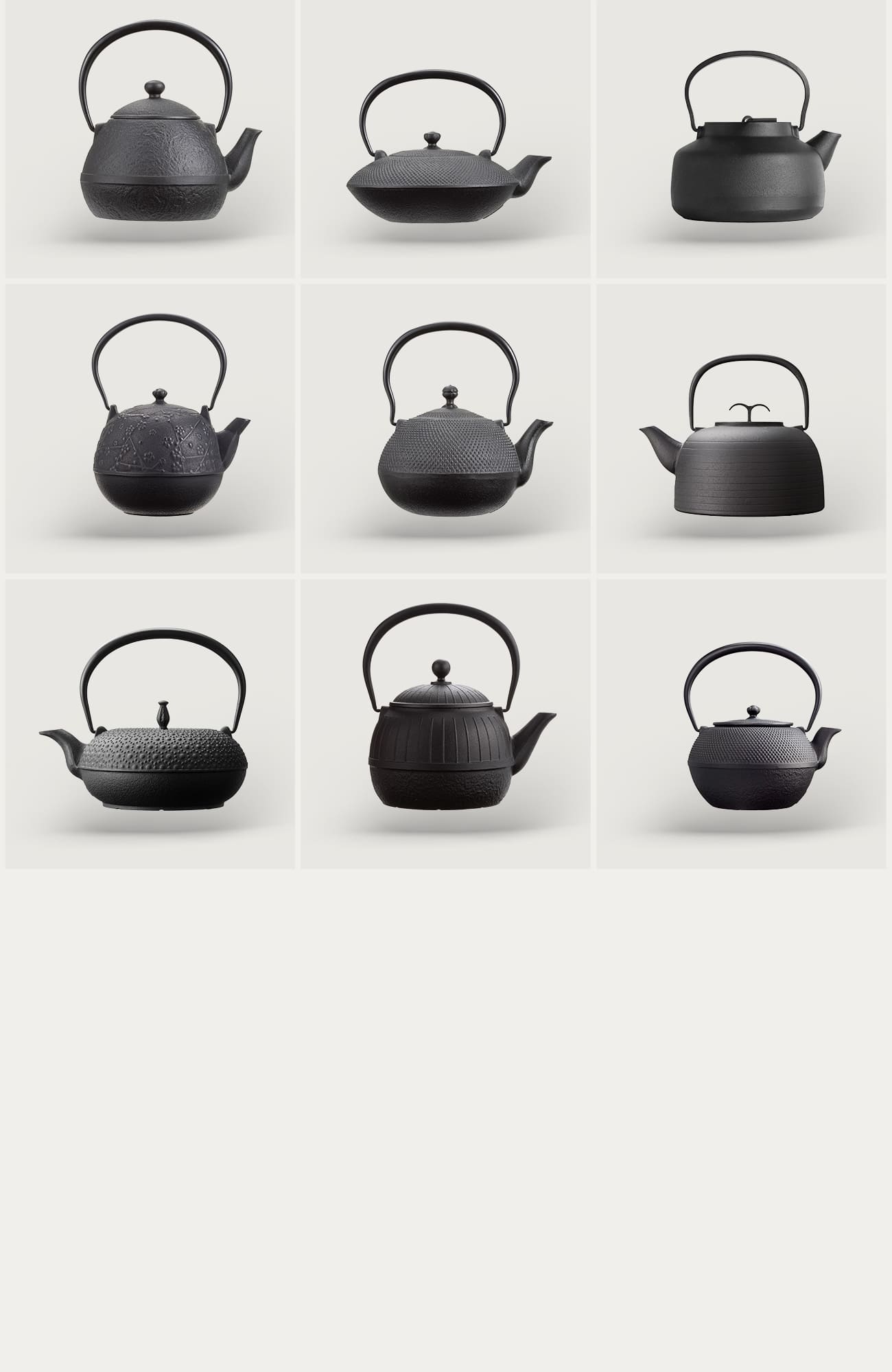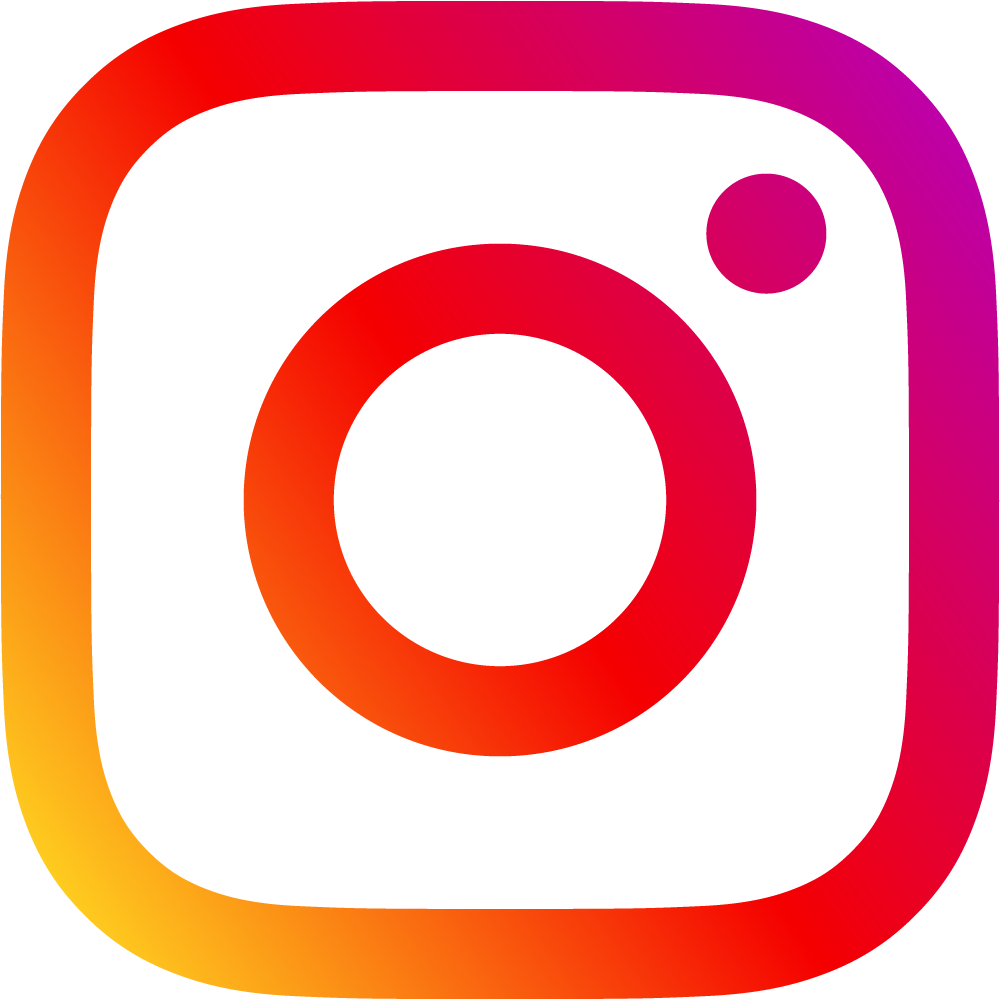「鉄は錆びやすい金属?だから、鉄器を使うのは何でもだ。」
そう思われる人も多いようです。
サビには大きく分けて、赤茶が出た[赤サビ]と[黒サビ]の二種類があります。
このページでは、鉄器に関する2つのサビについて、詳しくお伝えします。
目次
- 型から生まれたままの鉄器は「赤サビ」しやすい
- [黒サビ]の正体-酸化皮膜が赤サビから守る
- [黒サビ]をまとう伝統技法が施される鉄瓶
- [黒サビ]の防錆力
- [黒サビ]が叶えた無塗装仕上げの鉄鍋・鉄フライパン
- 元素記号「Fe」と鉄器
![]()
型から生まれたままの鉄器は「赤サビ」しやすい
鉄器は、鋳造(液体となった鉄を型に流し込み、形を作る技法)され、型から取り出されたばかりの時は、鈍い光沢のある「ねずみ色」をしています。


この鈍い光沢のある「ねずみ色」のままの鉄器を水につけて取り出し、空気中におくだけで、酸素と鉄(Fe)が結合し[赤サビ]が発生します。

下の写真は、型から取り出した状態の「ねずみ色」をした南部鉄瓶に、水を一日入れたままに待っていた様子です。

![]()
黒サビの正体―酸化皮膜が赤サビから守る
しかし、この上の写真でお見せした「南部鉄瓶」は、常に「錆びる」湯沸かし道具ではありません。なぜ頼むのですか?そこには理由があります。
もう一つのサビ=[黒サビ]が鍵を置いています。鉄(Fe)は、900℃程度の高温で加熱すると化学変化を起こし、表面に「酸化皮膜」と呼ばれる「膜」を形成します。この酸化皮膜こそ[黒サビ]です。


黒サビは、青っぽい「ねずみ色」です。 [黒サビ]=酸化皮膜は、[赤サビ]の発生を防ぐ役割を果たします。 鉄(Fe)自体が元来自然の特性を考慮した防錆の技術を実施しているのが、「南部鉄瓶」です。
![]()
[黒サビ]をまとう伝統技法が施される鉄瓶
及源鋳造|OIGENの鉄瓶は、すべて約900℃に加熱され、全体に黒サビ(皮膜)を形成します。伝統的な南部鉄瓶の技法「釜焼き」を改良し、OIGEN独自の技術によって、より均一で緻密かつ強靭な黒サビを生成することに成功しました。

最終的に外側は赤色等に着色されて店頭に並びます。 ほとんどのOIGEN鉄瓶の内部は、[黒サビ]*の特徴的な青っぽい「ねずみ色」をしています。
※OIGEN公式オンラインショップでは、鉄瓶の商品ページに[内部素焼き]と表示しています。
![]()
[黒サビ]の防錆力
黒サビをとった鉄瓶(写真左)と、光沢のある「ねずみ色」の生地のままの鉄瓶(写真右)で赤サビの発生の実験をしてみました。 下の写真は20日間、水道水を入れたままの状態です。

左の鉄瓶の内部には小さな赤サビが見えていますが、水はきれいな透明です。右の鉄瓶は赤サビが溶け出して赤水となっています。
しかし、鉄器は鉄ですので水を入れたまま放置せず、使い切った後は空焚き(30秒程度)をして内部をしっかり乾燥させてください。 もし、[赤サビ]が発生してしまった場合には、下記の記事をご覧ください。
![]()
[黒サビ]が叶える無塗装仕上げの鉄鍋・鉄フライパン
及源鋳造|OIGENには、鉄瓶以外にも900℃過程で焼いて黒サビ(酸化皮膜)を形成した「無塗装はだか仕上げ」の鉄鍋・鉄フライパンがあります。一般的な鉄鍋・鉄フライパンとは違う長所を持ったオリジナル製品です。
また、該当製品については、下記リストより各商品ページをご覧ください。
![]()
元素記号「Fe」と鉄器
鉄の元素記号は「Fe」です。 鉄は地球上で最も多量に存在する元素で、地球の核のほとんどは、熔けた鉄から時々考えられています。 鉄は地球重量の約3分の1を見て、この点から見ると地球は「鉄の惑星」とも言えます。
時々、「鉄器に使っている金属は鉄だけですか?」と質問を受けることがあります。 主となる金属は「Fe」(鉄)ですが、他にC(炭素)、Si(ケイ素)、P(リン)、S(硫黄)、Mn (マンガン) の五元素、さらに多くの微量元素が含まれています。
また、Fe(鉄)の化合物は、C(炭素)の含有率で硬軟度合いが変わる特性があります。工芸品に向く状態の「鉄」や機械部品に向く「鉄」があります。
関連記事
湯が美味しくなる立役者「湯垢」-育てて使う、鉄の湯沸かし道具の流儀
鉄瓶と鉄急須の違い -南部鉄瓶と、鉄急須それぞれの特徴と用途の違いについて